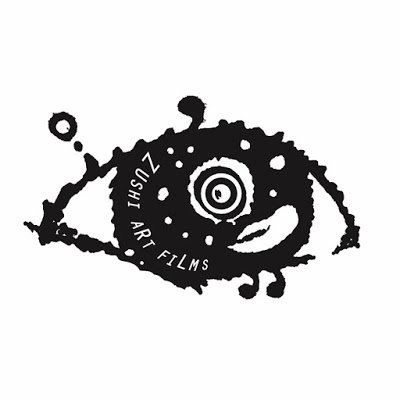奇しくも昨年「螺旋の映像祭」は台風というもう一つの螺旋の到来とともに開催されたが、それから一年以上経過してもなお、今年の「らせんの映像祭」が開催された2021年12月において、いまだ我々はCOVID-19のパンデミックという別の災害のただなかに生きている。COVID-19のパンデミックは、単なる感染症の流行にとどまるものではない。それは、根本的に日常の生活を変容するよう迫り、それに伴って、日常とは何か、世界とは何かという概念自体を変化させてしまうような体験であったのではないか。「終わりなき」ものとされていた日常はコロナ禍において、いつ終わってしまってもおかしくないものとなり、さらに、目に見えないウィルスにつねに晒される可能性のもとで生活を営んだり自宅で長期間他者から自己を隔離することを余儀なくされたりするなか、日常や世界は今までとは異なった側面を露わにすることもあるだろう。パンデミックの始まりからあまり時間の経過していなかった前回とは違って、今年の上映作品には、時間の経過とともにパンデミックに対して多少なりとも距離を持つことができるようになったためであろうか、直接主題にしているといないとに関わらず、コロナ禍の影がさまざまなところに見出されるものが多かった。そうした明示的・暗示的なコロナ禍の影とそれにも関連した日常の概念の変容に注目しつつ、今回の上映作品を一つひとつ見ていくことにしよう。

asamicroによる『egg life1:怪物』は、最初の緊急事態宣言発令下において、外出「自粛」を余儀なくされた二ヶ月の間に制作された作品であり、明示的にコロナ禍での生活がテーマとなっている。パンデミック下で自宅に長期間引きこもらざるを得なくなったとき、我々は、普段大して気にも留めていなかった生活上のさまざまな些事を改めて見つめる機会を思いがけずも得て、それらに目を開かれる思いをしたことが多くあったであろう。本作において、ダンサーであるasamicroは、自分でつくった双子の目玉焼き(作中で「カイブツ」と呼ばれる)という日常の些細なことからインスピレーションを受けて、自宅の台所で踊る。それは、新たに発見された日常生活の異常な細部から生み出されたダンスであると言うことができるだろう。

幸洋子の『June 4, 2020』もまた、コロナ禍における日常生活を取り上げた作品である。祖父の危篤、そしてCOVID-19の蔓延という特殊な状況もあって、作家が10年ぶりに愛知の実家で三ヶ月間過ごしたという出来事に基づいている。うたた寝をしている間に自分が木の床の一部となって床に取り込まれていくかのように感じたという話が途中語られるが、それは、緑一色の線で描かれる本作のアニメーションと同様、人と周りの物との境界線があいまいとなり、互いに溶け合ってしまうような体験である。そこでは、日常や世界はもはやかつてのようにはっきりとした輪郭を持つものではなく、自己と世界とが交感するような新たな存在のあり方が見出されている。外の世界へとあえて出ていかなくても、家のなかで日常生活にとどまり深く沈潜することで本作は逆に、「自分と世界との境界とは?」といった広大な問題へと接続していくのである。

村岡由梨の『透明な私』において、統合失調症を患う村岡は、現実が足下から瓦解する恐怖を不意に感じて大量服薬してしまい、入院することを余儀なくされる。今までしばしば会っていた人と急に会えなくなってしまうかもしれない、今までの生活が激変してしまうかもしれないといったように、「終わりなき」はずであった日常がコロナ禍で突然まったく異なるものになってしまう恐れに我々が晒されているのと同様に、村岡にとっても、世界は決して堅固ではなく、いつ足下から崩壊してしまってもおかしくないものなのである。本作はコロナ禍において撮影されたものではありながら直接的にそれをテーマとしているわけではないが、コロナ禍において我々が抱いている、日常や世界の崩壊への不安を、強度が高められたかたちでそこに見出すことができるだろう。

山下つぼみによる『かの山』は、離婚を決めた夫婦が、逗子で最後に過ごす一日を描いた作品であるが、ここにも今までの日常が明日から急変してしまうという終わりの感覚を異なるかたちで見てとることができる。夫婦の会話のなかで夫は何度も、さまざまな事柄に対してこれが最後だということを強調するが、口には出さないもののもちろん妻もそのことを十分認識しているのであり、本作におけるどの光景も終わりの感覚に満たされている。本作のなかでも風呂場でのシーンは特筆すべきだろう。夫は浴槽のなかにいて、妻はドアを隔てた脱衣所にいる。風呂場のその閉じられたドアが二人の間の心理的距離を象徴的に表している。夫はその距離を縮めようとするかのようにドアを開けて、一緒に風呂に入るよう妻を誘うが、妻はそれを断りドアを閉ざす。妻によるその行為は、二人が夫婦として一緒に生活するという日常を確実に終わらせる行為であったと言えよう。

池添俊の『朝の夢』は、自分の「母」であった祖母を主題とした作品である。池添は、年老いていく祖母の話を今のうちに聞いておかないと後悔すると思い、祖母のもとへと通って少しずつその声を集めていた。そこにもまた、祖母と会うのはこれが最後かもしれない、祖母が存在する世界が今にも終わってしまうかもしれないという感覚がある。本作において特徴的なのは、池添の祖母とは別の若い女性が映像に登場し、現代の風景の中において、祖母の話で語られる若い頃の祖母の行動をなぞっていることである。そして、祖母の若い頃の話は、祖母自身だけでなく、おそらくその若い女性のものであろう声によっても所々語られ、さらに、最後にある3分ほどの長回しのシーンでは谷川俊太郎の「ひろがり」という詩が、多少ずれつつも二人の声によって同時に読み上げられて、二人の声が時を超えて重なり合う。そのようにして、体調を崩した祖母の記憶の混濁を反復するかのように、年老いた祖母と若い女性、過去と現在とが作品のなかで混淆するのである。
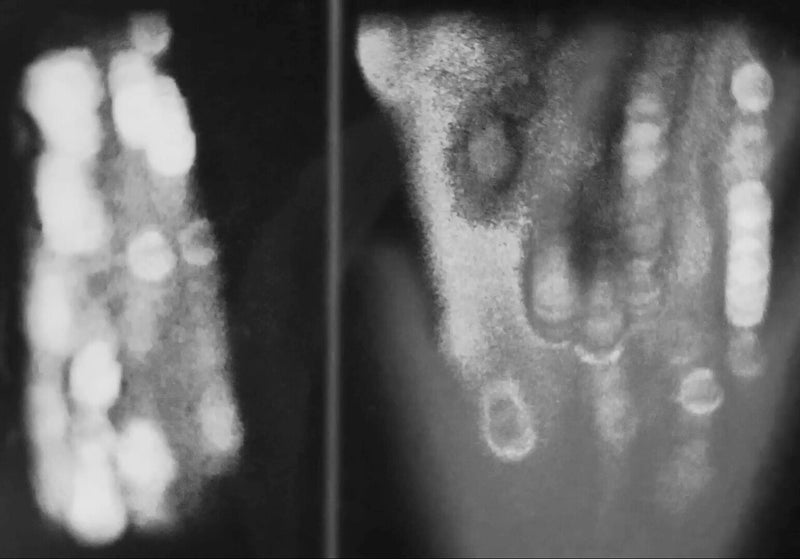
鈴木彩文の『Celer––––Melancholy Movement』もまた、記憶のなかにおけるイメージ同士の重なり合いを描いた作品であると言えるだろう。本作はCelerの楽曲のためにミュージックビデオとして制作されたものであり、彼の音楽が呼び起こす記憶の煌めきを表現しようとしたのだという。作品内において、燃える火や風に揺れる木々、細波立つ水辺、緩やかに動く手などのイメージが次々と緩やかにオーバーラップしていく。それはあたかも、記憶のなかにおいて個々のイメージの境界が不分明となり、それらが朧げに重なり合っているかのようである。

同じくオーバーラップという技法を用いているのは磯部真也による『13』である。本作は、16mmフィルムによって、沈んでいく太陽を同ポジション・同アングルからインターバル撮影と多重露光で映像に収めた作品である。そこでは単に、太陽の複数のイメージが重ね合わされているだけではなく、各々の太陽に伴う時間それ自体が一つの画面のなかに積み重ねられていると言えるだろう。大量の太陽がかたまりのようにして一緒に沈んでいく美しくも異様な光景には、5年という長い撮影期間の厚み、そしてオーバーラップによって示される世界の重層性が表現されているのである。

当たり前に思っている日常の世界に対して新たな別の層を見出しているのが吉開菜央と仲本拡史による『ナイト・シュノーケリング』である。まず本作において特徴的なことは、吉開と仲本が日常性や身体性と結びついた機材であるスマートフォンを用いて撮影を行なっていること、そして吉開と仲本との日常的なやり取りや撮影プロセスも作品内に収められていることである。その上で、地上からであったりライトがなかったりしたならば見ることのできない、夜の海中の光景が映し出される。その光景は、普段の日常や世界といったものの下の層にある別の世界であり、本作では、日常の層そしてその下にある普段見えない別の層といったような世界の重層性が描き出されているのである。

大西景太の『Requiem / composed by M.Cardoso』は、マヌエル・カルドーゾというポルトガルのルネサンス音楽の作曲家によってつくられた合唱曲「レクイエム」を視覚化したアニメーション作品である。この曲は、複数の独立した旋律が対等な立場で絡み合うポリフォニー音楽に分類される。音楽の構成にあまり馴染みのない人にとって、ポリフォニー音楽は、曲を聞いただけではそれぞれの旋律をうまく識別することができず、ただの音のかたまりのようなものに感じられるかもしれない。しかし、大西は、ポリフォニー曲である「レクイエム」における個々の旋律をアニメーションとして可視化することによって、どんな人であってもそれぞれの旋律を個別に把握し曲の重層性を認識できるようにしているのである。ポリフォニー音楽における重層性の認識というこうした体験は音楽という枠を超えて、日常的な世界の重層性や複数性を見出していくことにもつながるであろう。

ハブヒロシの『音の映画–––Our Sounds』もまた、音を通して世界の複数性を描き出している作品である。しかし本作は大西の作品とは違って、「音の映画」というタイトルの通り、映像はまったくなしで音のみで構成されている。そこでは、岡山県高梁市の日本語教室に集まった、ベトナムを中心とした海外から来た人々がハブヒロシのファシリテーションのもと一緒に歌を制作し、最後にそれを演奏し歌う。この歌は順にベトナム語、日本語、英語、フランス語で、それぞれの言語を母語とする人々によって歌われていくのだが、それら多様な言語をすべてきちんと理解できる人は観客にほとんどいないであろうし、「音の映画」であるためもちろん字幕もないので、少なくとも自分の理解できない言語で歌われた部分に関しては「意味のある言葉」ではなくただの「音」として聞かれることとなるだろう。しかし、歌が徐々につくり上げられていくプロセスをその前に耳にした上で、そうした知らない言語による歌を最後に聞くと、ただ理解できない雑音としてそれらを切り捨ててしまうことなく、依然として理解できないながらも、豊かな意味や響き、さらにはその背後に存在している、理解できないかもしれない他者の存在を否認することなく認めることができるようになるのである。

吉開菜央による『Shari』は端的に、複数のものの間に関わる作品であると言ってよいだろう。まずタイトルにある「Shari」とは、本作の舞台である、北海道にある斜里という町の名前であると同時に、「シャリシャリ」といった雪の擬声語にも由来している。さらに本作はドキュメンタリーであると同時にフィクションでもあり、本作の監督・ナレーターである吉開は同時に「赤いやつ」でもあって、すなわち人間とケモノの間の存在なのである。そして斜里という町も、人間が自然と近い関係において生活している場所である。さらに『Shari』という作品自体も、異常気象やコロナ禍といった、撮影時に偶然生じた出来事に開かれていてそうした他なる要素を躊躇なく取り込んでいる。このようにして、本作は、それぞれの要素が各々のアイデンティティに縛られることなく複数のあり方へと開かれていて、それら複数の項の間に存在する作品なのである。

坂本夏海の『Knitting the Intangible Voices』は、スコットランドのハイランド地方に伝わる女性労働歌「waulking song」をテーマに、繊維業における女性労働について考察した作品である。「ウォルキング(waulking)」という作業は、10人ほどの女性がテーブルを囲んで行うものであるが、かなりの重作業であり、それを軽減するために「waulking song」という労働歌がうたわれたという。ここでは、日常的に行われる辛く苦しい労働が坂本の映像によって、女性が行う共同作業という形象を通して、女性同士の連帯の可能性へと反転され接続される。すなわち、そこでは日常的な事柄のなかに潜んでいる抵抗の兆しが見出されているのであり、本作を見ることを通して我々も我々の日常において同様にそうした兆しを発見するよう促されているのである。
冒頭に記したように、COVID-19のパンデミックによって、我々は長期間自宅にとどまることを余儀なくされたが、同時にそれは、当たり前に思っていた日常や世界といったものを新たなやり方で見出すような体験でもあった。我々にとってそのことは、日常や世界が決して均一で一枚岩的なものではなく、そこには潜在するさまざまな層があることを、螺旋を上から下へ降りていくようにして発見する機会ともなったのではないだろうか。2021年12月に開催された「らせんの映像祭」は、コロナ禍がその苦境をポジティヴに反転させるチャンスともなり得ることを我々が作品を通して再認識する好機となったにちがいない。
菅原伸也|Shinya Sugawara
美術批評・理論。1974年生まれ。コンテンポラリー・アートそしてアートと政治との関係を主な研究分野としている。最近の関心は柳宗悦。主な論考に、「質問する」(ART iT)での、田中功起との往復書簡(2016年4月〜10月)、「岡本太郎の「日本発見」—岡本太郎の伝統論と民族」(『パンのパン 04』)、「タニア・ブルゲラ、あるいは、拡張された参加型アートの概念について」(ART RESEARCH ONLINE)がある。他には、奥村雄樹(『美術手帖』2016年8月号)やハンス・ウルリッヒ・オブリスト(Tokyo Art Beat)へのインタビューがある。@shinya_sugawara https://sugawarashinya.wordpress.com